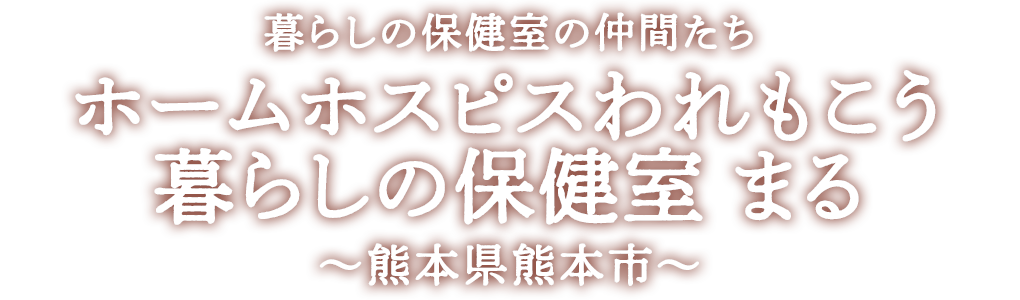コミュニティの特徴

-
熊本市は、熊本県のやや北部に位置する熊本県の県庁所在地。県の総面積の5.3%にあたる約390㎢に県内の42.8%にあたる約74万人が暮らす。2011年には九州新幹線が全線開業しアクセス良好な九州の拠点都市。2012年に政令指定都市に移行し、九州では福岡市、北九州市について3番目に人口が多い。
「日本三名城」の一つの熊本市のシンボル熊本城を臨む中心部には、百貨店や西日本最大級と言われるアーケードを備える繁華街があり、活気あふれる都市。上下水道のすべてを天然地下水でまかなう豊かな自然に恵まれ、さまざまな農産物の生産も盛んな地域。
中央区、東区、西区、南区、北区の5つの行政区がある。- ●豊かな自然環境に恵まれ、熊本城をはじめとする歴史遺産と伝統文化を受け継ぐ都市
- ●九州の中央に位置し、九州新幹線、高速道路、都市間バスの発達により、九州内の都市へのアクセスがよい立地で、市電やバスにより市内の交通網も整備されている
- ●熊本市の人口あたりの病院数が政令指定都市中1位(平成29年医療施設調査)であり、救急医療体制も整備されている。
- ●2016年の熊本地震から5年、仮設住宅への入居者の99%以上が住まいを再建し、復興を進めてきている
- 熊本市の基本データ(令和4年1月1日現在)
-
- ●面積:390.32㎢
- ●人口:731,683人
- ●世帯数:349,866世帯
- ●人口密度(2010年):1874.57人/㎢
- ●年齢3区分別人口
- ・年少人口(15歳未満):13.8%
- ・生産年齢人口(15~64歳):59.4%
- ・老年人口割合(65歳以上):26.8%
- 移動
-
九州新幹線を利用すると博多駅まで最速32分、鹿児島中央駅まで最速42分と短時間でアクセス可能。市内の移動は、1924年に開通した路面電車の市電が、市内を東西に走る交通網として市民や観光客に幅広く利用され、熊本桜町バスターミナルからは放射状にバス網も張り巡らされている。
- 社会資源
-
熊本市内には、三次救急医療を担う熊本大学医学部附属病院、国立病院機構熊本医療センター、熊本赤十字病院に加え、多くの二次救急医療を担う病院があり、24時間365日受け入れ可能な救急医療体制が構築されており、人口10万人当たりの病床数は政令都市中1位、医師数2位、専任救急隊数2位と医療資源が豊かな地域である。
暮らしの保健室まるの概要
設置主体
NPO法人 老いと病いの文化研究所われもこう所在地
〒862-0950 熊本市中央区水前寺5丁目17−18
アネシス水前寺1F電話番号
096-273-8585FAX
096-273-8584
暮らしの保健室の立ち上げ
- 立ち上げた人
竹熊千晶さん
NPO老いと病いの文化研究所われもこう 理事長
熊本保健科学大学教授 看護師・保健師・防災士
熊本生まれ。大学卒業後、天草で保健師。沖縄・横浜、アメリカ在住後、熊本に戻り、大学で地域看護学教員に。研究テーマは「障害や病気を持ったときどんなふうに暮らしていくことができるのか、最期の時をどこで迎えるのか」。2010年「ホームホスピスわれもこう薬師」、NPO法人「老いと病の文化研究所われもこう」を開設。同年ヘルパーステーション、2013年「われもこう新大江」、2020年訪問看護ステーションを開設。熊本保健科学大学「ちいき楽暮(ラボ)(地域包括連携医療教育研究センター」と看護学科の教員の兼務をしながら精力的に活動されている。
- 生まれたきっかけ
-
地域にある空き家を活用して何かできないかという思いと、宮崎のかあさんの家の市原美穂さんとの出会いがきっかけに、疾患の種別や性別、年齢に関係なく、介護が必要な人にとって最期まで安心して暮らせる家「ホームホスピスわれもこう」を2010年開設。また、NPO法人「老いと病いの文化研究所われもこう」として、看取りというケアを通して、地域のまちづくりにも寄与することを目的とした活動を開始した。ホームホスピスを初めて10年。ケアをする人たちが看取りを行っていく過程で、疲れてしまったり、これでよいのだろうかといろいろな思いが出てきて、退職に至ることもある中、ケアする人たちの思いを吐き出せる場所、そこからまた次に向かっていける場所が必要と考え、暮らしの保健室の開設へ。また、大学の教員たちが施設内に留まるのではなく、暮らしの保健室を利用して地域と繋がってほしいという思いも、もう一つの目標である。
活動の様子
- ホームホスピスの活動
ホームホスピスを開設して12年間で、16件の看取りを行った。看取り件数は決して多くはない。それは、主治医から紹介があって入所した人も元気になられて生活をする人が多いからだ。がんがあっても、認知症があっても、重複した疾患があっても元気に過ごし、共に生活をしている。家族も毎日来られたり、週末に泊まっていかれたり、住民の方も皿洗いをされたり、亡くなられた後の家族も来られて一緒に料理をしたりと、皆で支え合って生活している。認知症で徘徊がある方が夜に出かけ裏のおばあちゃんお家に入っていても、「うちのじいちゃんもこんなんだったから、よかよか。」と、認知症の人がいてもいい町になる。地域の中で人が亡くなる、認知症になることも隠さずに生活をしていたら、他者への気遣いができてくる。ホームホスピスをしていることで看取りの文化を伝承していきたい。
- コロナ禍でのホームホスピスへの相談
暮らしの保健室まるは、開設準備中であり、具体的な展開はこれからである。ホームホスピスでは、これまでも入居相談や介護家族の相談を受けてきた。コロナ禍では病院や介護施設で面会が制限されてしまい、介護家族から面会にも行けないという家族からの相談が多く、看取りに関して悔いなく送りたいという家族のニーズが、コロナの面会制限によってより大きくなっている。ホームホスピスでは、普通の家なので密にならず、動線も確保できるため、感染対策をしながら家族皆で看取ることができており、ホームホスピスでの看取られた家族は満足されている。ホームホスピスという選択肢があることを地域に情報発信する機会も得ている。
- ケアを行うスタッフの相談の場としての暮らしの保健室を
ケアを行うスタッフが看取りを行っていく過程の中で疲れたり、これでいいのかと思ったり、ジレンマや葛藤が生じたり、時には家族に責められたり、対象者への怒りを感じたりといろいろなことが出てくる。ホームホスピスを運営してきた経過の中で、このような状況を「何とかせんといかん」という思いの方々が集まったことで暮らしの保健室の開設へとつながった。療養者を支えるケアスタッフを支えるシステムが必要と考えている。ケアスタッフの悩みを共感したり、感情を受け止める場所、ある程度吐き出した上で自分を取り戻すことができる場、緩和ケアのサロンとして、看取りの文化を育て、情報発信をしていきたい。よかよかと丸ごと受け止めてをめざして「まる」をやろうと思っている。
- 保健医療福祉職の育成の場としての暮らしの保健室へ
医療職のほとんどが活動の場が病院であることから、医療系の大学教員も地域に出ていくことはなく、地域に関心がなかった。しかし、ある時、大学の所在する地域の保健センターの赤ちゃん健診の時に、お母さんたちの骨密度や血糖値の測定するため、検査技師の教員の協力を得て地域に出てもらうことができた。この機会をきっかけに大学教員も地域に出て行く意識を持ってもらえるようになり、現在では、暮らしの保健室で「検査カフェ」としての活動を計画し、研究メンバーとして参加してもらえるようにし、整えている段階である。
暮らしの保健室まるを訪ねて
大学で教鞭をとりながら、ホームホスピスを運営され、時には夜勤スタッフも担っているという竹熊さん。ほっそりとしたその身体のどこにそんなバイタリティがひそんでいるのかと圧倒されつつ、熊本の地に根を張り看取りの文化を伝承するのだという竹熊さんの看護実践に感動した。地域の文化までも創っていくこと。これこそが地域看護活動であるのだと。
誰もが通る「老い」「病い」「死にゆくこと」に対して看護としてどのように支援していくことが可能であるのか?竹熊さんのその問いは、「ホームホスピス」という現場で、本人とその家族への真摯なケアはもとより、地域住民や専門職としっかりと繋がり、共に支え合いながら活動を積み重ねられていた。竹熊さんの実践は地域の人々を支え、また地域の人々から支えられて発展してきており、これもまた地域看護活動の醍醐味である。
その実践の中で掴んだニーズと、その実践で繋がった素晴らしい人脈が集まり、新たに「暮らしの保健室」がスタートしようとしている。これまで地域に参加してこなかった病院中心の教員の「暮らしの保健室」での活動や教育がどのように発展していくのか大変興味深い。
取材日:2021年11月
レポート:米澤純子 撮影:神保康子